�����̑傫��
�g�b�v���������ʐ^�Ɋւ���R����
�ߘa8(2026�j�N
1��
�E��
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
- �m�i�V�_�l�j
- �~�����̎������ƁA���Ɂu�m�v�ƌĂ����̂������Ă��܂��B�~�̎�̒��ɂ���u�m�v�́A�u�V�_�l�v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B���ɕ{�V���{�̓V�_�l�Ƃ��čՂ��Ă��鐛�����^���A�~���D��ł������ƂɊW���Ă���悤�ł��B
- �����̂Ȃ��߂ŗ��߂ɂȂ�܂ɉ̂����u�����i�����j�����@���Ђ�������@�~�̉ԁ@��i���邶�j�Ȃ��Ƃďt�ȖY�ꂻ�v�ƁA���^�����Ĉ��̂����ɋ����瑾�ɕ{�܂Ŕ��ł�����~�`���͗L���ł��ˁB
- ���ɕ{�V���{�̖{�a�̉E���Ɂu�~�̎�v�[�ߏ�������̂�m���Ă��܂����H�u�×����A�V�_���܂��h��ƌ����`�����Ă���܂��~�̎��e���ɂȂ�ʗl�ɔ[�߂鏊�ł��v�Ƃ���܂��B
- �~�̐m�ɂ́A�A�~�O�_�����Ƃ����������܂܂�Ă��āA�̓��ŕ��������ƃV�A�������f�i�_�K�X�j���������A���ŏǏ�������N�����\��������Ƃ����Ă��܂��B�������A���n�����~��~�����ɉ��H���ꂽ�~�̐m�͐H�ׂĂ����͂Ȃ������ł��B
���E�o�C
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
�l�十�� �c�t�̃W���`���E�Q�i�����ԁj�A�ẴN�`�i�V�i���q�j�A�H�̃L�����N�Z�C�i���؍ҁj���O�十�ł��B����ɓ~�̃��E�o�C�i�X�~�j�����Ďl�十�ƌ��������ł��B���E�o�C�͂��̖��̒ʂ�܂�Ń��E�H�̂悤�ȉ��F���Ԃ��炩���A�Â���������̒������Y�̗��t��ł��B

- ���̎����̃��E�o�C�̖ɂ��Ă��鍕�������A�O�N�x�̉Ԃ̎��i���m�ɂ͋U�ʂ������ł��j�ŁA���Ɏ킪�����Ă��܂��B�u�X�~�v�́u�~�v�̕����������Ă��܂����A�~�Ƃ͂܂������ʎ�ł��B���E�o�C�̎�q�ɂ̓A���J���C�h�Ƃ��������L�Ő���������H�p�͋֎~�ł��B
�g�x�m�Ɩ���

�ߘa7�i2025�j�N
12��
�E���V���E�~�J��
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
- �~�J���̔�
- ��i�`���s�j�c�~�J���̔���������������̂��Ƃ����A���{��Ǖ��Ɍf�ڂ���Ă��鐶��ł��B�g�߂ȂƂ���ł́A�������h�q��J���[���ɂ��p�����Ă��܂��B
- �����l���c�݂���̔�̕\�ʂɂ���I�����W�F�̏����ȓ_�X�i���E�j�ɂ���A�V�R�̖F�������ł��B���ɂ͂悭�n���鐫��������A���܂≻�ϕi�ɂ��z������Ă��܂��B
- �u�E���V���E�~�J���ɂ��āv�A�u���������~�J���̌��������v�ɂ��Ă͈ȑO�̃R�������������������B
�@�@�����ߘa5�i2023�j�N11���̃R����
11��
���~�W
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
- ����C�V�쎌�A�������Ȃ̏��́u�g�t�i���݂��j�v�̂P�Ԃ̉̎��́u�H�̗[���ɏƂ���܂��݂��E�E�E�E�v�ł����A�H�̗[���ɏƂ炳��Č�����̂́u�Ƃ�R�^���~�W�v�Ȃ̂��u�Ƃ�^���}���~�W�v�Ȃ̂��A�̂���C�ɂȂ��Ă��܂������A���ׂĂ݂Ă�������܂���ł����B�������Ɂu�e�����}���~�W�v�Ƃ������O�̃��~�W�͂���܂��A���{�̃��~�W�́u�C���n���~�W�v�u���}���~�W�v�u�I�I���~�W�v��3��ނɑ傫���������邻���ł��B���āA�̎��̃��~�W�͂ǂ���ł��傤�ˁE�E�E
����C�V�������̍g�t�̔������ɍ쎌�����ƌ����Ă���A�M�z�{���ɂ������F�약�w�ɍs���ă��~�W�����Ă݂����ł��ˁB - ���ۂƂ��Ẵ��~�W�^���̂Ƃ��Ẵ��~�W�@�ɂ��Ă͈ȑO�̃R�������������������B
�@�@�@�@�ˁ˗ߘa5�i2023�j�N11���̃R����
10��
�}���~�i�^�|�E�h�j
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
- �}���~�͖{���A���{�̎R��ŕ��ʂɌ�����ŁA�V�Ղ�₩���g���A��łĂ��Ђ����ȂǁA�V����t�͎R�Ƃ��ĐH�p�ɂ���Ă��܂����B�����ۂ�4���̉ԕق����Ԃ͏������ڗ����܂��A����10�`11���ɏn���܂��B�n����4�Ɋ���A�U�N���̂ԂԂ������Ɏ����A��ԐF�̎�������o���܂��B���͐H�ׂɗ��܂����A�l�ԂɂƂ��Ă͗L�łȂ̂Ő�ɐH�ׂĂ͂����܂���B
- �ނƂ��Ă��k���ŔS�肪����A�×���肱�̖ŋ|����������Ƃ���u�^�|�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B�ꕶ���㑐�n���`�O���ɂ����Ă̈�ՂƂ��ėL���ȕ��䌧�̒��l�L�˂���́A���ۂɃ}���~�ō��ꂽ�|���o�y���Ă��܂��B�@�@→→���䌧�j
- �}���~�͒h�Ƃ������A�Ñ�ɂ����ẮA�Ⴂ�}�̎���@�ۂ������Ƃ��āu�h���v������Ă��܂����B���݁u�d���v�́A���i�R�E�]�j�������Ƃ��č��ꂽ�k�ɏ�̂����L���鍂���a���̂��Ƃ��w���܂��B�@
�����ޗǍ��������ف@���q�@�W�p�����u�d���v�@�@�@�ˁ��S���肷���a���A����u���q�@�̎������a���̌��_�v
�N��
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
- �N���͓ꕶ���ォ����{�l�ɐe���܂�Ă����A���ł��B�O���ێR��Ղł͒��a1m�̃N���̖̒���A��ʂ̌I�̉ʔ炪�o�y���܂����B�ԕ����͂ɂ��W���̎��͂ɐl�H�I�ȌI�т�����Ă������Ƃ��������Ă��܂��B�ꕶ�l�ɂƂ��āA�H�ƁE���z���ށE�R���Ƃ��ďd�v�Ȏ����������悤�ł��B���オ�������Ă��A��������̌��z���ނƂ��āA�S���̖��Ƃ��āE�E�E�N���̖͎g���Ă��܂����B

- �}�����O���b�Z��}�����N���[���Ƃ����i������A�N�����p��ł����ƃ}�������Ǝv���Ă��܂������A�p��ŃN���́uchestnut�i�`�F�X�i�b�g�j�v�ł����B
�umarron�i�}�����j�v�̓t�����X��Ƃ������Ƃł����A�{���t�����X��Łumarron�i�}�����j�v�́A�N���Ƃ悭�����Z�C���E�g�`�m�L�i�}���j�G�j�̎����w���umarron�i�}�����j�v�������ł��B�������A���̃}�����͏a�����ߐH�p�Ƃ��Ă͎g�p����Ă��܂���B
���[���b�p�O���ŃC�K�̒���2����3�̏����Ȏ��������Ă���̂��uchataigne�i�V���e�[�j���j�v�A1�̑傫�Ȏ��������Ă���̂��umarron�i�}�����j�v�ƌĂ�Ă��āA������̃}�����Ń}�����O���b�Z������邻���ł��B
�X��
�t�E�Z���J�Y��
 �@�@�@�@
�@�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
- �k�A�����J�암���Y�́A�t�F���X�Ȃǂɗ��݂��Ȃ���ɖ���鐫�̈�N���ł��B �Ղ�����ƕ��D�̂悤�ȉʎ����ł��ă��j�[�N�Ȃ��Ƃ���A�Ϗܗp��̃J�[�e���Ƃ��č͔|����Ă��܂��B
- ���̓^�l���������Ă�����̂̋ɂȂ��Ă��āA�Ԃ��ƃp���Ɗ���܂��B�^�l�͋��`�Ŕ����n�[�g�`�̖͗l������K���R�������Ă��܂��B
- ���̕t�����c�������邭�銪���ă��[�X�ɂ�����A��̃n�[�g�ɖڂ����`���Ƃ�����Ƃ��킢����i�ɂȂ�܂��B���������E�E�E
�C�k�^�f�i�����A�A�J�}���}�j
 �@�@�@�@
�@�@�@�@
- �C�k�^�f�́u�C�k�v�͎��̂����ǂ�ł��傤�B
A.���̂̈Ӗ��������t�F�����i�C�k�U�����C�j�A�����i�C�k�W�j�j�A�Z�Z�̌��i�C�k�j�E�E�E
B.�{�������A�قȁi���ȁj�E�ہi���ȁj�̈Ӗ��������t�F�C�k�U���V���E�A�C�k�z�I�Y�L�A�C�k�c�Q�E�E�E
C.���́Z�Z�Ɏ��Ă���F�I�I�C�k�m�t�O���A���~���i�C�k�J�L�j�A�����i�P���V�j�E�E�E
����B�F���i�M�^�f�Ƃ����������Ɏg��ꂽ��ނɑ��āA�C�k�^�f�͐h�������Ȃ����߂����Ăꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�@�@�@�@���i�M�^�f�̉萶��������̂��̂���^�f�Ƃ����A���ł��h�g�̂܂Ɏg���Ă��܂��ˁB
�@�@�@�@�u���H�������D���D���v���������i�M�^�f�ł��B - �A�J�}���}�A�A�J�m�}���}�i�C�k�^�f�̕ʏ́j
���H�A�����̕��̎��g�F�̉Ԃ��炩���܂��B ���̗���̉Ԃ����������A�Ԕтɂ݂��ĂāA�܂܂��ƂɎg���ėV���Ƃ���A�e�n�Łu�Ԃ̔сi�܂�܁j�E�Ԃ܂܁v�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�u�Ԃ܂܁v�u�Ԃ̂܂܁v�u�����̉ԁv�͏H�̋G��ŁA�����q�K�⍂�l���q���r��ł��邻���ł��B
8��
�C�l
 �@�@�@�@
�@�@�@�@
�u�R���͒m���Ă���B���Ă��m���Ă�B�����������Ƃ���B�ł��A���̃C�l�ɉԂ��炢�Ă���̂��������ƂȂ��B�v�Ƃ����l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�C�l�ɉԂƕ����āA�悭����A���̉Ԃ̂悤�ȁA���ɉԂт���v�������ׂ�̂Ō������ƂȂ��Ǝv���̂�������܂���B�܂��A�炢�Ă��鎞�Ԃ��Z���̂����R�̈���Ǝv���܂��B
- �G�C�i�n�j�c���̉Ԃł͂����ׂ�߂��ׁE�q�[����邽�߂ɃK�N��ԕق�����܂����A��̉Ԃɂ́A�K�N��ԕق��Ȃ��G�C�ƌĂꏫ�����݊k�ƂȂ镔��������܂��B
- �J�ԂƎc�ΐF�̃G�C�i���݊k�ɂȂ镔���j���c��2�Ɋ���āA���̒����甒�������ׂ��Ƃяo���Ƃ��ꂪ�J�Ԃł��B�����ׂ̐�[�ɂ͉��F���ԕ������Ă��܂��B�����āA�߂��ׂ̓G�C�̓����ɂ���A���ɔ���ꂽ�ԕ��ɂ�����ƃG�C�͕��܂��B �J�Ԏ��Ԃ�2���ԂƂ����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�ˁ�����@�C�l�̉ԁ@����̂����݁iNHK for school�j
6��
�X�C�����i���@�j
 �@
�@ �@�@�@
�@�@�@ �@
�@
���F�n�X�A�E�F�X�C����
- 2023�N�̂W���̃R�����Ɂw���O�̂����́A�u���J�Ԃ��A�ߌ�ɉԂ����̂��A��(�˂�)��ƌ����ĂĐ��@�Ɩ��Â���ꂽ�v�Ƃ����܂��B�x�Ə����܂����B�ł��A�n�X�i�@�j�̉Ԃ��ߌ�ɂ͉Ԃ���Ă��܂��܂��B
�@�@�ˁ����v���c�@�l�s�c�s�Y�ƁE�����E�X�|�[�c�����������cHP�u�@�ɂ��āv - �X�C�����i���@�j�ƃn�X�i�@�j�̂��āA�����ł͘@�i�����Q�j�ƌ��������ł��B�D�̒��ň炿�A���̓D�̉���ɐ��܂邱�ƂȂ��������Ԃ��炩����@�͕����ł͂����ւ�ɏd�v������Ă��܂��B
- ���Ă���X�C�����ƃn�X�ł����A��Ƃ��Ă͂͂܂������ʂł����A�n���s�i�����R���j����s�E�t�E�ԑ�E��܂ŐH�p�ƂȂ�n�X�ɑ��āA�X�C�����̓A���J���C�h���܂�ł���ꍇ�����邽�߁A�H�p�ɂ���邱�Ƃ͋H�������ł��B
�A�W�T�C
 �@
�@ �@
�@
�z���A�W�T�C�@�J�V���o�A�W�T�C�@�A�i�x��
- �ߔN�b��̔����A�W�T�C
- ���}�炫�c���{���Y�̃K�N�A�W�T�C�₻�ꂩ��i����ǂ��Đ��܂ꂽ�{�A�W�T�C�A�t�̌`�������I�ȃJ�V���o�A�W�T�C�Ȃǂ́A�Ԃ��炢���N�ɐL�т��}�ɏH�ɂȂ�Ɖԉ��t���A���N�̂U�����ɉԂ��炩���܂��B�H�ȍ~�ə��肷��ƍ炫�܂���B
- �V�}�炫�c�A�����J���Y�̃A�i�x���́A���̔N�̏t�ɐL�т��}�ɉԉ��t���܂��B�~�ə��肵�Ă��Ԃ��炫�܂��B
5��
�o��
- �o���̞��i�Ƃ��j
- ���ꂢ�ȉԁi�o���j�ɂ͞�������Ƃ����܂����A���͉��̂��߂ɂ���̂ł��傤�H�H
- ���H��������g����邽�߂Ƃ�����������܂����A��Ԃ̓G�ł���A�u�����V�ȂǁA���ɂ͖��ɗ����Ȃ��ł��ˁB
- �s��}�̓]�|��h���t�b�N�I�Ȗ����ł͂Ȃ����Ƃ�����������܂��B�o���̌���̑����͂鐫�̐A���ŁA���������ł͏�ɐL�тĂ������Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA��������Ɉ����|���ď�ɐL�тĂ����炵���ł��B
�m���Ƀo���̞��͉������ɋȂ����Ă��܂��ˁB�q�ǂ��̂Ƃ��A�o���̞���@�̓��ɂ������āu�T�C�����v�ƗV���Ƃ��v���o���܂��B
 �@�@�@
�@�@�@
- ���c�Βn�牑
- 2025�N�t�̌��J:5��8���i�j�`5��25���i���j
- �A�N�Z�X�F⇒⇒���c�Βn�牑�@�����u�A�N�Z�X�v�@
- �����F���������A���ԗ����F1000�~
- ����̃C�x���g�F
�E5/17�i�y�jCherish Ballet Theatre�i�o���G�j12:00�`12:35�A13:30�`14:05
�E5/18�i���jMachida Jazzoo Quintet�i�W���Y�j10:50�`11:30
�@�@�@�@�@�@�g�� ��E���эG�� JAZZ DUO�i�W���Y�j12:10�`12:50�A13:30�`14:10
�E5/24�i�y�jBloom Saxophone Quartet�i�T�b�N�X�j12:10�`12:50
�E5/25�i���jMaple Special Quartet�i�T�b�N�X�j10:50�`11:30�A12:10�`12:50
�@�@�@�@�@�@��c���w�Z�E�`�A�_���X���i�����j14:00�`�i�u���O�́`14:20�AHP�́`14:30�j - 5/24�i�y�j13:30�`15:00�@�o���u�K��@��a�c�G���搶�u�~�j�o���~�͂��y���ށv�@�����@�撅40��
- ���̑��F�L�b�`���J�[�o�X�i�����j�A�s���u�[�X�o�X�i�y�E���j �@�Z�C�x���g�E�u�K��E�o�X���@�ڍׂ́@�@�ˁ����c�Βn�牑�����u���O �@⇒⇒���c�Βn�牑����HP
�t�W�i���j�ƒ��ǂ��̃N�}�o�`
 �@
�@ �@
�@
- �̂̑傫�ȃN�}�o�`���t�W�i���j�̉Ԃɓ���˂����ނƁA�N�}�o�`�̏d���ŁA�B��Ă����߂��ׂƂ����ׂ��o�Ă��܂��B�N�}�o�`�������z���Ă���ԂɁA�����ɂ����ׂ̉ԕ�������������悤�ɂȂ��Ă��܂��B
- �t�W�����ɍs���ƁA�H�����̂��傫���N�}�o�`�����ł��邱�Ƃ������ł����A�N�}�o�`�͉����ȖI�Ŏ�������U�����Ă��邱�Ƃ͂܂�����܂���B�܂��A���I�Ńz�o�����O���Ă���N�}�o�`�̃I�X�i�I�X�������ɔ����O�p�̖͗l������܂��j�͐j�������Ă��܂���B
4��
�i�V
 �@�@�@
�@�@�@
- ���\�Y
����26�i1893�j�N��t�͌����i�����s�j�̓����C���Y�i�����u���\�Y�v�j�̗����Ŕ������ꂽ���ŁA�����悭���Y�ł��������ߐl�C�i��ƂȂ�A�ꎞ�͑S���̗��͔|�ʐς�60���ɂ܂ōL�������Ƃ������Ƃł��B
�@�@�ˁ����s�u���킳����̕V�[�g�@���\�Y���̂ӂ邳�Ɓv - ���ƕs�a����
�o���ȉʎ��̑����́A�����̉ԕ����߂��ׂɕt�����Ă������Ȃ�Ȃ��u���ƕs�a�����v�Ƃ��������������Ă��邻���ŁA�ق��̗��̉ԕ������Ƃł����Ƃ��������܂���B
�@�@�ˁ����s�����u�l�H�����ɂ��āv
���Ȃ݂ɁA�\���C���V�m���o���Ȃł��̂Łu���ƕs�a�����v������A��Ŏq�����c���Ȃ����߁A���ׂẴ\���C���V�m�́A�u�ڂ��v�ő��₵���N���[���ł��B ���̂��߂��ׂĂ̌̂�����ɋ߂������������A���̐������ɑ������߂Ɂu�T�N���̊J�ԗ\�z�v�Ɏg���Ă��܂��B
�~�c�o�`
 �@�@�@
�@�@�@
- �����Ƀj�z���~�c�o�`�ƃZ�C���E�~�c�o�`�肷�邽�߂ɂ́A�������������uY���v���uH���v���Ō�������炵���̂ł����A��ʓI�ɂ̓I�����W�F���ۂ��̂��Z�C���E�~�c�o�`�ō����ۂ��̂��j�z���~�c�o�`�ƌ����Ă��܂��B
- ������Ƃ�閨�ʂ��������ƂƁA�������x���J������Ƃ������X�g���X�ɋ������߂ɁA�{�I�Ƃɂ̓Z�C���E�~�c�o�`���D�܂�邻���ł��B
- �~�c�o�`�̓V�G�X�Y���o�`���A�j�z���~�c�o�`�͔M�E�I���Ƃ����Z�ŎE���܂��B���{�e�n�Ŏ��炳��Ă����Z�C���E�~�c�o�`�ł����A�Z�C���E�~�c�o�`�͂��̋Z���ł��Ȃ����߁A���{�̂قƂ�ǂ̒n��Ŗ쐶�����Ă��Ȃ������ł��B
3��
�n�N���N�����ƃR�u�V

�n�N���N����
�E�Ԃт�i�Ɍ�������́j�c9���i�Ԃт�6���Ɣ���������3���j
�E�ԁc�J������Ȃ��A������ɍ炭�B
�E�R�u�V���A��⑁���炭

�R�u�V
�E�Ԃт�c6���i�K�N�Ђ͗Ȃ̂ʼnԂт�Ƌ�ʂł���j
�E�ԁc�J������A�������Ə�������������č炭�B�Ԃ̉��ɗt�i�ʏ��1���j�������B
�E����4�`5���Ə��Ԃ�
 �@
�@
�V�f�R�u�V
�E���F����W�g�F�̉Ԃ��炩��
�E�Ԃт�c12�`24��
�E���{�ŗL��B�쐶��̐�ł��뜜����邪���|�p�Ƃ��č͔|����Ă���B

�^���V�o
�E�Ԃт�F6��
�E�Ԃ̉��ɗt�͂Ȃ��B
2��
�̉�
.jpg) �@
�@.jpg) �@
�@.jpg) �@
�@.jpg)
- �̉�=�A�u���i�ȃA�u���i���̉Ԃ̑���
�A�u���i�A�L���x�c�A�^�J�i�A�J�u�A�R�}�c�i�A�n�N�T�C�A�J���t�����[�E�E�E�݂�ȍ̉�
�A�u���i���̉Ԃ͂ǂ�����F�Ŏ��ʂ��Ă��邱�Ƃ���A�Ԃ�����Ɓu�̉ԁv�ƌĂ��X��������܂��B
�ʐ^������u�L���x�c�v�u�J�u�v�u�����v�u���v - ���́u�O����v�́u�̉Ԕ��v�̉Ԃ�
�u�O����i���ڂ�Â���j�v�̍쎌����������C�V�́A���쌧�o�g�Ŗ��ɕʑ��������Ă����̂ŁA���̍̉Ԃ͖��i�J�u�̈��j�̍̉Ԃ����m��܂���B
�~
- ���~�ƍg�~
�u���~�v�Ɓu�g�~�v�́A�Ԃ̐F�ŋ�ʂ��Ă���̂ł͂Ȃ������ł��B�����Ԃ́u�g�~�v��Ԃ��Ԃ́u���~�v�����݂��邻���ł��̂ŋ����ł��B�~�̖̒f�ʂ������ۂ��̂��u���~�v�Ԃ��ۂ��̂��u�g�~�v�Ƃ���邻���ł��B�܂��A�O�ς���͐��m�ɂ͂킩��܂��A�u�g�~�v�͐V�����L�т��}�i�V���j���Ԃ��ۂ��A�u���~�v�͗��ۂ��X�������邻���ł��B
�@�@�ˁ��u������ЃO���C�v�v�����y�[�W�@�@�@ - �����炫�i1�{�̖ɐԂƔ��̉Ԃ��炭���Ɓj
�E���͏����̈�`�q�ψقʼnԐF���ς��₷���A�g�~�̎}�̂ǂ����̍זE�ɓˑR�ψق��N����Ɣ��ԂɂȂ邱�Ƃ�����A���̐�̉Ԃ͂��ׂĔ��ԂɂȂ�̂������ł��B�~�̉Ԃ͖{�����F�ŁA�ӏܗp�Ƃ��ĕi����ǂ���g�~�����܂ꂽ�����ł��̂ŕ����I�Ɍ��X�̐F�ɖ߂����̂�������܂���B
1��
���E�o�C

- �X�~�F�������Y�ō]�ˎ���ɓ�������܂����B�u���E�o�C�v�́A�����́u�X�~�v�̉��ǂ݂Ƃ���A���F�̉Ԃ��������ŘX�H�i���E�U�C�N�j���v�킹�A�~�̉Ԃ̂悤�ɍ��肪�����A�ԕ����Z���}�ɂ܂Ƃ܂��Ă����߂ƌ����Ă��܂��B
- Winter sweet:1������2���ɍ炭���E�o�C�́A�H�̃L�����N�Z�C�ł��Ȃ��A���t�̃W���`���E�Q�ł��Ȃ��A�~�̉Ԃ̊Â�����ł��B�Y�o���A�p�ꖼ�́uWinter sweet�v�B�������A���Ɏ�q�ɂ͗L�Ő����J���J���`�����܂܂�Ă��܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B
�ԕx�m�ƍg�x�m

- �ԕx�m�i�����ӂ��j
�E�ԕx�m�Ƃ����A�����k�ցu�x�ԎO�\�Z�i�v�V���[�Y�́u�M�������v���v�������ׂ���������Ǝv���܂��B�u�M���i���앗�j�v�̐����ӉĂ̕��i��`������i�ƌ����Ă��܂��B
�E�ԕx�m�Ƃ́A�ӉĂ��珉�H�ɂ����Ă̑����ɁA�_�▶�ƒ��z�Ƃ̊W����x�m�R���Ԃ����܂��Č����錻�ۂ����������ŁA�u�ԕx�m�v�͉Ă̋G��ł��B

- �g�x�m�i�ׂɂӂ��E�����ӂ��j
�E�g�x�m�Ƃ́A�^�~�̒��[�A�x�m�R�����Ⴕ����Ԃœ��ɏƂ炳��Ԃ����܂�A�N�₩�ȍg�F�ɐ��܂�x�m�R�����������ł��B
�ߘa6�i2024�j�N
12��
��i

- �H���i�u�[�����˂̒n�u���s�v
�E���ԏ�L�̂����߃r���[�X�|�b�g�F
�@�@���}���G���i���{��i��Y�j�A����������i�t���A�X�^�b�O�̉��j�Ɛ������i�i�g���E�����j
�E�����ߍH��i�ʖ��t���j�F�z���C�g�L���b�X���A�F���X�e�[�V�����A�����E�T���E�~�b�V�F���@
�@�@�@�����S���H���i�s�s���c��@�u�H���iINFO]�@���̍H���i���
�Z���s�c�o�X��HP�ɂ́u�V��ŐH�ׂĐ��H���i�Ϗ܁I����y���߂�ՊC�����V�R�[�X�v�Ƃ����s�o�X���g�������w�R�[�X�Ă�����܂��B�@�������s��ʋnj���
�Z���s�ό������HP�ɂ́A�u���H���i�o�X�c�A�[�ŐV���v�̃y�[�W������܂��@�������s�ό�������� - �C���~�l�[�V����
�Ekirara���A�[�g������c�V�S�����u�w����̃f�b�L�A�k���̕��ؓ��ȂǁA�w���ӂ��C���~�l�[�V�����ōʂ�
�E�L�����f�b�L�C���~�l�[�V�����c�a���w�O�f�b�L�A���ӂ̒ʂ��r���Ȃǂ��C���~�l�[�V�����ōʂ�
�E�W���G���~�l�[�V�����c��݂��胉���h�S�̂��C���~�l�[�V�����ōʂ���
�E���̑��ALA CITTADELLA�A�s�����ʂ�ȂǗl�X�ȏꏊ�ł��E�E�E�E�@
�Z���c�̓��W�y�[�W�@�u�N���E�N�n�ɍs���Ă݂悤���v�ɂ��A�C���~�l�[�V���������f�ڂ��Ă��܂��B
11��
�J�L

- �ŌÂ̊Ê`�i�T���ہj�͐�萶�܂�
���q����O���̌���2�i1214�j�N�Ɍ��݂̐��s�����扤�T���n���A���h�R���T���̎R���Ɏ������Ă������̂��������ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B
1889�N�̒������{�s�ɂ��A����E�I�E�Е��E�ܗ͓c�E�Ñ�E�������E�㖃���E�������E���T���E�����10��������������Ċ`�������a�����܂����B�V���̖��̂́A�`�̐��Y�������ւ����Ƃ��痈�Ă��邻���ł��B
�@�������s�����u�T���ۊ`�v �@�@�����������@������Y�I�����C���u�T���ۊ`�v - �a�`
���͏a�`�͊Ê`�������x�����������ł��B�������A�a�݂̌��������i���n���^���j���j����ύ��Z�x�ŁA���Ɋ܂ނƑ��t�ɂƂ�����ȏa�݂������܂��B�������A�a���ɉB�ꂽ�Ö������A�����`�Ƃ��邱�ƂŋM�d�ȕۑ��H�Ƃ��ė��p���Ă������j�́A�ޗǎ��ォ�瑱���Ă���Ƃ����Ă��܂��B���̏a�������������̂̐l�̒m�b�͈̑�ł��ˁB
10��
�L�N

- �e�i�L�N�j�́A���ǂ݁H�P�ǂ݁H
�e�͒�������`�������A���ŁA���Ƃ��Ɠ��{�ɂ͎������Ă��܂���ł����B���̂��߁A�e������킷�a�ꂪ����܂���ł����B���̂��߁u�L�N�v�͉��ǂ݂ɂȂ�܂��B
�@�@�Q�l�����@�������u�Џ��q��w�u�e�ɂ܂�邨�b�v�@�Ȃ� - �U���M�N
���c���s�v��ɂ���l��̂���e���i��؎O�Y����j�Ō��J����A�m����悤�ɂȂ����L�N�i�e�j�̈��ŁA�i��ł͂���܂���B�Ԃ��U���̂悤�ȃh�[���^�ɍ炭���Ƃ��疼�t�����܂����B�P���ɐ���̏��e���d�Ȃ�傫�Ȕ�����`���܂��B �@�@�@�������c���s�����u����e���i������j�v
�Z�C�^�J�A���_�`�\�E

- �ԕ��ǂ̌����H
�Z�C�^�J�A���_�`�\�E�́A���a40�N��ȍ~�ɑS���ő�ɐB���܂����B���̍��A7������10���̉ԕ��ǂ̌������ƌ������܂����B�������A�Z�C�^�J�A���_�`�\�E�͕��ʼnԕ����^�ԕ��}�Ԃł͂Ȃ��A����ɉԕ�����r�I�d���ԕ��̗ʂ����Ȃ����߉ԕ��ǂƂ͖��W�ŁA�{���̔Ɛl�́A���������ɉԂ��炩���u�^�N�T��I�I�u�^�N�T�Ȃǂ������������ł��B - �A�����p�V�[�F�A�������̐A���̐�����}���镨������o������A�������������h������A�������肷����ʂ̑���
�Z�C�^�J�A���_�`�\�E�́A���{�̐A���ŏ��߂ăA�����p�V�[���F�߂��܂����B�X�X�L�����̓y�n�ɔɐB���Ă����A�����쒀���Ă����܂����B �������A�ߔN�ł͋쒀����Ă����X�X�L�����A�����̏ꏊ�Ő��͂����Ă��܂��B�@
�@ �ڍׂ� �@�@�@�����R���ȑ�HP�@→���{�A�������w��HP�@�A���p���`
9��
�I�~�i�G�V
 �@
�@
- �H�̎����@�i���ܒ����Ɗo���₷���ł��j
�u�n�M�E�L�L���E�A�N�Y�E�t�W�o�J�}�A�I�~�i�G�V�A�I�o�i�E�i�f�V�R�A�H�̎����v
�t�̎����́A1��7���ɂ����ɓ���ĐH�ׂ܂����A�H�̎����͑S�ĉԁB�p�����łāA�߂����₷���G�߂̓�������Ԃ��̂������ł��B�i�I�o�i���X�X�L���ԕ�i�J�X�C�j�ƌĂ��Ԃł��B�j - �I�~�i�G�V�i���Y�ԁj���O�̗R��
�I�~�i�i�����������j�G�V�i�w�V�F���j�����������������|�������������B�����̃I�g�R�G�V�i�j�Y�ԁF�ʐ^�E�j�ɔ�ׂ₳�������������邩��B�Ȃǂ̐�������܂��B
�X�X�L

- ���H
�H������ł�7���`9���Ƃ��Ă���A����7�����u���H�v�A����8�����u���H�v�A����9�����u�ӏH�v�Ƌ敪���Ă��܂����B �u���H�v�ƈႢ�u���H�v�͏H�S�̂̒����A8��15���������w�����t�ł��B���͑��z��Ɋ�Â����܂邽�߁A���H�̖����̓��͖��N���t���ς��܂��B
2024�N��9��17���A2025�N��10��6���ƂȂ邻���ł��B - �������ƃX�X�L
�]�ˎ���A�������͎��n�Ղ⏉��Ղ̈Ӗ������������Ȃ�A�����Ɉ�����n�ł�����т��������A���ӂ�����Ƃ��čL�܂����悤�ł��B�{���̓X�X�L�ł͂Ȃ����������Ă��܂������A�\�ܖ�̎����ɂ͈�䂪�Ȃ����Ƃ������A����Ɍ`�����Ă���X�X�L���g����悤�ɂȂ�܂����B - ��N�x�̃R�����u�X�X�L�E�I�M�E���V�v��������������
8��
�c���N�T

- �^�e�[�}�p�[�N�̃L�����N�^�[�̎��̂悤�ȁA�傫��2���̐��Ԃт炪�ڗ��c���N�T�́A�����ꖇ�����Ԃт�����Ɏ���3�ԕق̐A���ŁA���A�W�A�̉��тɍL�����z���鑽�N���ł��B
- �c���N�T�̐F�F�f�́A���ŏ����鐫���������Ă��܂��B���̐����𗘗p���āA�c���N�T�̈��́u�����ȁv�̐F�f���A�̂���F�T����i����߂̉��G�Ɏg���Ă��������ł��B
- �F�f�����p�ł��邾���łȂ��A�c���N�T�͐H�p�ɂ��Ȃ�܂��B�N�Z��A�N���قƂ�ǂȂ��A�ǂ�Ȓ����@�ɂ��悭�����Ƃ����܂��B�_�炩���t��s�͐��̂܂܃T���_�ɂ�����A��łĘa�����₨�Ђ����A�ςт����ɂ�����B������u�ߕ���|�̕��A�V�Ղ�ȂǁA�����ȃo���G�[�V�������y���߂邻���ł��B
- �G���ȂǂƂ������玸��ł��ˁB
7��
�z�I�Y�L�i�S���A�S���A�_���j
 �@
�@
- ���{�ł͐̂���e���܂�Ă����悤�ł�
- �S���A�S���c�S���͒̂悤�Ɍ����邱�Ƃ���A����c�l�⎀�҂��Ɍ����Ă��A���d���I�ɏ��镗�K������܂��B�S���̖c������́A���~�̊Ԃ���c���܂��߂����Ƃ����Ă��܂��B
- �_���i�J�K�`�j�c�Î��L�ł̓��}�^�m�I���`�̖ڂɂ��Ƃ�����B
�w�u���̖ڂ͐Ԃ������̂悤�ŁA��̐g�̂ɓ������A����������܂��B���̑̂ɂ͑ۂ�q�m�L��X�M�������A���̒����͔��̒J�A���̎R�ɓn��A���̕�������ƁA��ʂ��������ɂ܂݂��ࣂ�Ă��܂��v�Ɠ������B�y�����ɐԂ������Ƃ����̂́A���Ō����_�݂ق��Â��̂��Ƃł���B�z�x�i�Î��L�E������ƒ��߁`���{�_�b�A�_�ЁA�Ñ�j�A�Ì����j - �Ԏ_���i�A�J�J�K�`�j…���{���I�ł͉��c���Ð_�̖ڂɂ��Ƃ�����
�w�@�������A�w�������A���E�K���P���Ă���A��͑傫�ȋ��̂悤�ɋP���Ԃ��ق������i�Ԏ_���j�Ɏ���A�Ƃ����B�x�i���w�@��w�u�ÓT�����w�v���Ɓ@�_���f�[�^�x�[�X���j


�V�I�J���g���{
-
�@�V�I�J���g���{�ƃ��M�����g���{
- �悭�m���Ă��܂����A���M�����g���{�̓V�I�J���g���{�ł��B�V�I�J���g���{�̎��Ɩ����n�̗Y�́A���F�ɏ����ȍ������䂪�U�݂���̂ŁA���Ƀ��M�����g���{�i���m��x�j�Ƃ�Ă��܂��B


-
�@�V�I�J���g���{�i���h��x�j�Ɖ��h
- �ʐ^�����Ă��킩��ʂ�A�W����܂���B
�Y�͐��n����Ɣ��������܂Ƃ��悤�ɂȂ�A���̕������Ɍ����Ă��̂����O�̗R�����Ƃ����Ă��܂��B������O�ł����A�r�߂Ă������͂��܂����A�ŋ߂̌����ŕ������O���˂��鎖���������܂����B����ɂ��^�Ă̓������̉��ł����C�Ɋ����ł��邻���ł��B�ŋ߂͂��̎��O����AUV�J�b�g�ł��ˁB
6��
�}���[�S�[���h
- �R���p�j�I���v�����c
���Ԃ┺�����Ӗ�����u�R���p�j�I���v�ƁA�A����\���v�����c�����������t�ŁA�R���p�j�I���v�����c�́u�����̂����A���v��u�����ƂȂ�A���v�Ƃ������Ӗ��������܂��B
�}���[�S�[���h�͓Ɠ��̍��肪����A���ɂ̓Z���`���E�Ȃǂ̒��������ʂ������Ƃ���A�R���p�j�I���v�����c�Ƃ��ėL���ł��B
�}���[�S�[���h�̍����番�傳��鐬���́A�Z���`���E�ɂƂ��ēŐ��������Ă��܂��B���̂��߁A��ƈꏏ�Ƀ}���[�S�[���h��A���Ă������ƂŃZ���`���E���������A�y������ꂢ�ɂ��Ă���܂��B �܂��A�}���[�S�[���h�̓Ɠ��̍���́A�ꕔ�̊Q��������������ʂ����邻���ł��B�R�i�W���~���������A�ꕔ�̃A�u�����V���Ȃǂ��}���[�S�[���h�̍���������ƌ����Ă��܂��B
�A�W�T�C
- ���z�Ԃ��A�W�T�C�Ɠǂނɂ͖���������?!
�u���z�ԁv�Ə����āu���������v�Ɠǂނ̂́A������\�L��a���ɓ��Ă����{��Ǝ��̓��Ď��ł��B
���z�Ԃ̕����́A�����̓�����̎��l�A�����Ձi�͂����傢�@���{�ł͔��y�V(�͂��炭�Ă�j�̖��Œm���Ă���j�̎��ɓo�ꂵ�Ă��܂��B���������̊w�҂ł��錹���i�݂Ȃ��Ƃ̂��������j���A�u����̓A�W�T�C�̂��Ƃ��낤�v�ƁA���̊������u�A�W�T�C�v�Ƃ����悤�ł��B
�����̊��Ⴂ����A�A�W�T�C�̊������u���z�ԁv�ɂȂ�܂����B
5��
�V���c���N�T
- ��̃c���N�T
- �l���i�c���N�T�j�c�}���ȃV���W�N�\�E���B�ʖ��N���[�o�[�B�ߘa5�N5���̃R�����ɂ��ڂ��܂������A�]�ˎ���ɗA���i�̔��̋l�ߕ��Ƃ��ꂽ�Ƃ��납��A���t����ꂽ�Ƃ����܂��B
- �ܑ��i�c���N�T�j…�i�f�V�R�ȃc���N�T���B�t�����̒܂Ɏ��Ă���Ƃ��납��A���t����ꂽ�Ƃ����܂��B
 �@�@�@
�@�@�@
�V���c���N�T�͐H�ׂ邱�Ƃ��ł���́H
�l�b�g�ŃV���c���N�T�̂��ƂׂĂ���ƁA�u�V���c���N�T�͐H�ׂ���쑐�v�Ƃ��ďЉ�Ă���T�C�g�A�u���̃N���[�o�[�́A�H�ׂ���_���I�v�Ə�����Ă���T�C�g�A�u�H�p�ԁi�G�f�B�u���t�����[�j�v�Ƃ��Đ��̗t���ς�̔����Ă���T�C�g…�Ƃ��܂��܂ł��B
�N���[�o�[�̃n�`�~�c�͒m���Ă��܂����A�{���ɐH�ׂĂ����C�Ȃ̂ł��傤���H�H�H�H
�������������́u�N�������f�[�^�[�x�[�X�v�̃V���c���N�T�̃y�[�W�ɂ́w�ƒ{�����ʂɐH�ׂ�ƃV�A�����������L�Q�x�Ƃ���܂����E�E�E�@�@�����������������́u�N�������f�[�^�[�x�[�X�v�̃V���c���N�T�̃y�[�W
��ϋ����[���y�[�W�������܂����B���S�Ƃ́A���X�N�Ƃ͂ɂ��čl���������܂����B
�E�E�E
�֍�u�j���������ł��ˁB�ł̂Ȃ��A���͂����ł������ċt�ɕ��������Ȃ邮�炢�B�v
�u�Ƃ������A�قƂ�ǓłȂ�ł����ǁA���̒��ł��Ő��̒Ⴂ���̂�I��Ŗ�ɂ��ĐH�ׂĂ���Ƃ��������������Ǝv���܂��B���ɒ�ɍ炢�Ă���ԂƂ��́A�قƂ�ǂ��ł��܂�ł��āA������A�ʂł�����ƐH�ׂ�̂͂�����ł����B�v�E�E�E�i�F������w��w�@�_�w�����Ȋw�������@���p�����Ȋw��U�����j
������������͔`���Ă݂Ă��������B
��������w��w�@�_�w�����Ȋw�������@�H�̈��S�Z���^�[
�@��31��T�C�G���X�J�t�F�u�����Ă݂悤�I�[�H�ׂĈ��S�H�A������鉻�w�����[�v�J�Õ@→→�Y���y�[�W��
�I�I�C�k�m�t�O��

- �@�I�I�C�k�m�t�O���́A���ƎƑ��Ǝ̗���������A���ł�
- ���Ǝc�I�I�C�k�m�t�O���̉Ԃ͏������ԕ��͂������ׂ��ł��B�������߂Ē�������ƒ��̏d�݂ʼnԂ��h��܂��B���͗��Ƃ���Ȃ��悤�ɂ��ׂɂ����݂��܂��B���̎����̑̂ɉԕ������ԕ��͑��̉Ԃɉ^��܂��B
- ���Ǝc���Ǝ��ł����A�Â��Ȃ�Ԃт炪���悤�Ƃ���ƁA�I�V�x�̂₭�i�ԕ��������Ă��镔���j�����V�x�Ɉ����������܂��B
�@����̌���U��グ���悤�Ɍ�����̂��I�V�x�ł��B���̊Ԃɂ���ׂ��̂����V�x�ł��B
-
�@���O
- �C�k�m�t�O�������{�̍ݗ���ł��B���̃C�k�m�t�O�������Ԃ��傫�ȊO������I�I�C�k�m�t�O���Ɩ��������̂��A���w�҂̖q��x���Y�ł��B
- �C�k�m�t�O�������̉A�X�i���ؐ}���Ȃǂ̍]�ˎ���̐}����}���ɁA���̖��O�����邻���ł���…������ƂȂ�…�j
- ���̓������܂�ɂ��u������ƂȂ��v�Ȃ̂ŁA����Ȗ��O������悤�ł��B
���l���q���u������ƂȂ��v�ƍl������l�����E�E�E�@
�@�@�w���ʂӂ��萯�̂܂������@���Ȃ�i���l���q�j�x

�Q�lHP�@�@������c�s����WEB�@���Ԑ}�Ӂu�C�k�m�t�O���v �@�@�@������c�s����WEB�@���Ԑ}�Ӂu�I�I�C�k�m�t�O���v
�@�@�@�@�@�������t�@�����X�����f�[�^�x�[�X�u����ڍׁv�@������
4��
�Q���Q
- �W���a���i�w���̑���ɗp�����鐶���̓��{�ꖼ�́j�̓Q���Q�i���_�p�j�B�����Q�i�@�j����Q�\�E�i�@�ؑ��j�̕ʏ̂��悭�����܂��B
- 4������A�c��ڈ�ʂɃ����Q���L���镗�i���v�������ׂ���������Ǝv���܂��B����́A�O�N�̏H����킴�킴��q���܂��āA�_�Ƃ������Q�\�E�₵���̂ł��B�����̓��{�l�̌����i�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
- �}���Ȃ̐A���͍��ɍ����ۂ������̂������A�y���̒��f�����ɒ~���ēy���엀�ɂ��鐫��������܂��B���̂��߁A�x�k���̓c����엀�ɂ���ړI�ŐA�����Ă��܂����B�Ԍ�͂��̂܂ܓc���ɍ�������ŗΔ�Ƃ��Ă��g�p����܂������A���݂ł͌����悭�����엿���g�p����A�����Q���͂قƂ�nj��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
- �u�엿�O�v�f�v ���f�iN�j�͗t�ƌs�̐����ɁA�����_�iP�j�͉ԂƉʎ��̌`���ɁA�J���E���iK�j�͍��̐����ɕK�v�ȗv�f
 �Ԃ���ނ�F�c���N�T����Q�̂悤�Ɍs�̒����Ԃ�҂�ŁA�����Ȏq�ł��ӊO�ƊȒP�Ɋ��i����ނ�j����邱�Ƃ��ł��܂��B�����̂�����́A�l�b�g�Łu�Ԃ���ނ�v�Œ��ׂĂ݂Ă��������B
�Ԃ���ނ�F�c���N�T����Q�̂悤�Ɍs�̒����Ԃ�҂�ŁA�����Ȏq�ł��ӊO�ƊȒP�Ɋ��i����ނ�j����邱�Ƃ��ł��܂��B�����̂�����́A�l�b�g�Łu�Ԃ���ނ�v�Œ��ׂĂ݂Ă��������B

3��
����g��ƃ\���C���V�m
- ����g��
- ����g�삪�L�܂����̂́E�E�E
�C���[�W�I�ɂ́A�]�ˎ�����v�������ׂ�l����������̂ł����A�]�ˎ��㖖���ɍ]�ː��䑺�i���E�����s�L����j�̐A�؉����u�g����v�Ƃ��Ĕ���o�����Ɠ`�����A1900�N�i����33�N�j�ɐA���w�҂̓���ɂ�����g��Ɩ��t����ꂽ�����ł��B - ����g��͑S�ăN���[��?!
�N���[���i�S���������`���ƈ�`�q�g�����p���ʂ̌́j�Ƃ����ŐV�̉Ȋw�̃C���[�W�ł����A�{���̈Ӗ��́u�}���v�������ł��B�u����g��v�͐��䑺�̐A�ؐE�l�ɂ���Đڂ��ő��₳��A���E���ɍL�����������`���ƈ�`�q�������ł��B - ����g��̗��e�́E�E�E
��`�q�����ŁA��e���G�h�q�K���A���e���I�I�V�}�U�N���̎�ԎG�킾�Ƃ킩���Ă��܂��B
 �@�@�@
�@�@�@
- �\���C���V�m
- ��e���G�h�q�K���~���e���I�I�V�}�U�N���̎q�ǂ��́A�u����g��v�ł͂Ȃ�?!
�����e���琶�܂�Ă������q�����܂�Ȃ��悤�ɁA�G�h�q�K���~�I�I�V�}�U�N�����獡�́u����g��v�Ɠ����`���E������`�q�͒a�����܂���B �ł��A�G�h�q�K���~�I�I�V�}�U�N���̎�ԎG��̊w����Cerasus �~yedoensis�ƕ\�L���A���̘a�����u�\���C���V�m�v�ƌĂ�Ă��܂��B - �u����g��v���m���|�����킹����H�H�H
������`�q���m�Ȃ̂ŁA���ł��Ȃ��̂ł��E�E�E�E�B
- �u����g��v�Ɓu�\���C���V�m�v
�G�h�q�K���~�I�I�V�}�U�N���̎�ԎG��̈���u����g��v�ŁA�G�h�q�K���~�I�I�V�}�U�N���̎�ԎG��͑��ɂ��������݂��邻���ł��B
2��
�T�N���i���j
���{�Ɏ�������T�N���̖쐶��͉���ށH �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�@������@�@���}�U�N���i�R���j�@�A�I�I���}�U�N���i��R���j�@�B�I�I�V�}�U�N���i�哇���j�@
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�@������@�C�J�X�~�U�N���i�����j�@�D�G�h�q�K���i�]�˔ފ݁j�@�E�}���U�N���i�����j�@
 �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@������@�F�^�J�l�U�N���i������j�@�G�`���E�W�U�N���i�������j�@�H�~���}�U�N���i�[�R���j
 �@�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������@�I�J���q�U�N���i������j�@�J�N�}�m�U�N���i�F����j
���v���c�@�l���{������̉��HP�ihttps://www.sakuranokai.or.jp/chishiki/�j������ƁA��L�̇@�`�H9����w�䂪���̎R��Ɏ�������쐶��̊�{��Ƃ����9��x�Ƃ��ćI�����Ă��܂���B���v���c�@�l���{�Ԃ̉��HP�u���}�Ӂv������Ɓihttps://www.hananokai.or.jp/sakura-zukan/�j�A�w�����\�L�E������B�����암�A��p�ɕ��z���Ă��܂��B����̐Ί_����v�ē��ł������܂����A�O�����玝�����܂ꂽ�\�����L��A���Ƃ��Ǝ������Ă������̂Ȃ̂��������Ă��܂���B�x�Ƃ���A��������쐶�킩�珜����Ă���悤�ł��B
�J�̃N�}�m�U�N���́A�Ȃ�ƐV���Ɍ��������쐶��ł��B
�_�ѐ��Y�Ȃ̍L��aff��2023�N3�����œ��{�̍������W�ihttps://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2303/index.html�j����Ă��܂��B�w1���I�Ԃ�ɐV���Ȗ쐶�킪���������I�x�̋L���ɂ́w2018�N3���A�I�ɔ����Ŗ�100�N�Ԃ�ɍ��̐V�����쐶�킪�������ꂽ���Ƃ����f�B�A�Ȃǂŕ��A�傫�Șb��ƂȂ�܂����B�x�Ƃ���܂��B
�W��̓����́A�ǂ����10��ށi11����Ƃ��������悤�ł����j�Ƃ������Ƃł��傤���B
���s�Ɣ~

- �K�� �����̔~/��K����
- �K��̖k���Ɉʒu���鏬����т́A��������ɔ~�̖����Ƃ��ėL���ɂȂ�A�ϔ~�̂��ߖ����V�c���s�K�i��K�j���ꂽ���j������܂��B�u��K�v��u�K��v�̖��̂́A���̂��ƂɗR�����Ă��܂��B
- �����̔~�́A�]�ˏ����ɏ��c������^��A�����ꂽ�Ƃ̌����`��������A�ꎞ��30�����i��30ha�j���߂�܂łɂȂ�܂����B �����V�c�̍s�K���̔~�т́A�V�����T���A �i�����h�[����1.5���j�̍L���̔~�т����������ł��B �@�@�������s�K������u��K�����~���i���߂�����j���Ɓv�i2018�N8��7���j
�@�@�����u��K�����~�����Ɛ��i�v��v�i2017�N2���j
�@�@�������s�K������u�ߘa5�N�x��K�����w�ϔ~��x���J�����܂��I�v�i2024�N1��23���j�c�J�ÁF�ߘa6�N2��17��
- �v�n�~�ь���
- ��3,800�u�̉����ɂ�20��40�{�̔~�̖����݂��Ă���A2�����{����3�����{�ɂ����čg���̉Ԃ��������炫�ւ�܂��B�����ɂ͖k�����H���^�Ӗ�S���̂��߂ɉr�������܂ꂽ�̔������܂��B
�@�@�����_�ސ쌧�����iKanagawa Travel Info�j�u�v�n�~�ь����v
�@�@�������ʎВc�@�l���s�ό���������@�ό��X�|�b�g�u�v�n�̔~�сv

- ���c�Βn�@�~��
- ���c�Βn�̔~����2,500�u�̔~���ɂ͓��m�Ӂi�݂�����ׁj�� �����O�i�ӂ��ڂ���j�Ȃǂ̍g�~�┒�~���������������܂��B
�@�@�������c�Βn�����u�e�{�݂̂��ē��v�~��
�@�@�������c�Βn�����u�~���}�b�v�v
1��
�x�m�R
-
�������Ɍ��鉏�N�̗ǂ����̂̑�1��
- ��x�m�@���@�O�֎q�i�]�ˎ���ɍL�܂����Ƃ����A������ǂ����x�X�g3�I�j
�@�l�ȍ~�́A��������܂��B�ڍׂ�m�肽�����͂�������������������@�������t�@�����X�����f�[�^�x�[�X��
�i���t�@�����X�����f�[�^�x�[�X�F����}���ق��S���̐}���ٓ��Ƌ����ō\�z���Ă��钲�ו��̂��߂̃f�[�^�x�[�X�j - �����͂����閲�H�@
�@��A�����猳���c�]�˂ł͌Â��͑�A���̖����w�����悤�ł��B
�A��������2���c�N�z���̖�͐Q�Ȃ��K�������邱�Ƃ���A�V������茳������Q���̒��̖��ƂȂ�A
�B2������3���c���܂��܂Ȏ������͂��߂�u���n�߁v�̓��Ƃ��āA�Q���̖�Ɍ��閲�������Ƃ���悤�ɂȂ����A�Ƃ�����������܂��B
�@�@�������t�@�����X�����f�[�^�x�[�X��
�̉ԁi�����̑��炫�̉ԏ��j

-
��ȎR�̍̉��i�ʐ^��1/8�B�e�j
- �u�̉ԃE�H�b�`���O�v�i�U�����̑��炫�̍̉Ԃ̊J�Ԃɍ��킹�čs����C�x���g�B�j �@1/13�`2/18
������{���ό���������u�u��ȎR�@�̉ԃE�H�b�`���O2024�v�p���t���b�g�͂����炩��v
�_�ސ쌧���@�ԂƗ̂ӂꂠ���Z���^�[�u�ԍK�[�f���v
- �y�ԍi�n�i�i�j�z�e���s��������ԍf�i������j�͋��s�̓`����Ƃ��Đ�ԗp��Е��p�Ƃ��ČÂ����痘�p����Ă��������ł��B���O�̌Ăѕ��͈Ⴆ�ǁk�ԍK�[�f���l�ɂ҂�����̍̉Ԃ��������猩����ɂȂ�܂��I
�����ԍK�[�f�������@2024�N1��6�� (�y)�f��
���{��s ����͂܉Ԃ̍�
- �Ǘ����߂��̉Ԓd�ł̓i�m�n�i���J�Ԃ��܂����
�T�i��̎���u�����h���Ă���d�킵�Ă���̂� �R�����܂ŊJ�ԃ����[���Ϗ܂ł���悤�ɂ��Ă��܂��
��������͂܉Ԃ̍������@2023�N12��28���i�j�̉ԏ��
����C�̎���� �\���C���̋u
- �G���g�����X�ł́A�i�m�n�i�������ł��B���Ɨ[���͕x�m�R���y���߂�m���������ł��B
�����\���C���̋u�����@�J�ԏ��@2023�N12��29������
�ߘa5�i2023�j�N
11��
�E���V���E�~�J��
-
�����@�@�ȁF�~�J���ȁ@�@���F�~�J���� �@��F�E���V���E�~�J��
- ���݁u�~�J���v�ƌĂ����̂́A�E���V���E�~�J���i���B�����j�������܂��B�炪�����Ăނ��₷���A�H�ׂ₷�����Ƃ������ł��B���܂��܂ȍ͔|�i�킪����A�Y�n�ɂ���ău�����h��������܂��B
- �ꕔ�A�w�������玝���A�����J���L�c�̃^�l������������i�݂��傤�j�Ƃ��Ĕ��������x�Ƃ̐����f�ڂ��Ă���y�[�W������܂����A���݂́A���{���Y��Ɛ��肳��A��ʂɎ����������Y�Ƃ���邱�Ƃ������ł��B
�@�@�@�����_�ѐ��Y��HP
�u���������~�J���̌��������v
- ��̃L���E�E�E��ɂ́A�������̂ԂԂƂ����u���E�v�ƌĂ����_�������ɑ��݂��܂��B���̃L�����ׂ�����ׂ����قǁA�Â��݂���ƌ����Ă��܂��B
- ��̐F�E�E�E���z�̌��������Ղ藁�тĔ�̐F�����Z���I�����W�F�ɂȂ����݂���͂��Â݂������Ă���ƍl�����܂��B
- ���̑����E�E�E������������݂���͐��������܂�ʓ��ɑ���ꂸ�A�����Ïk����ĊÂ݂������Ȃ�܂��B�܂��A�w�^���ΐF�ł͂Ȃ����F�ɋ߂��قǁA�悭�n���Ă��ĊÂ��݂���ł���\���������Ȃ�܂��B
- �`�E�E�E�ʎ��������猩���Ƃ��ɁA�����̑ȉ~�`�i�G���`�j�ɂȂ��Ă���݂���̕����Â��X��������܂��B�݂���̉ʎ��͉��ɐ�������Ƃ��ɊÂ���~����ƌ����Ă���A�����ł��邱�Ƃ͊Â���~���Ă���؋��Ȃ̂ł��B

JA�O�P���iJA�݂����уI�����C���V���b�s���O�j���
���~�W
- ���ۂƂ��Ẵ��~�W
- �́A�H�ɂȂ葐�̗t���g�≩�F�ɐF�Â����Ƃ��u���݂��i���݂Áj�v�ƌ����������ł��B���́u���݂��i���݂Áj�v�Ƃ�����������A�F�Â��t�̂��Ƃ̂������Ƃ��āu���~�W�v�Ƃ��Ă�����悤�ɂȂ����悤�ł��B
- �g���ς�邱�Ƃ��g�t�Ə����āu�R�E���E�v�ƌĂсA���F���ς�邱�Ƃ����t�Ə����ē������u�R�E���E�v�ƌĂт܂��B���F�ɕς�邱�Ƃ����t�Ə����āu�J�c���E�v�ƌĂԂ̂ł����A������3����ʂ��邱�Ƃ�����A�܂Ƃ߂āu�g�t�i�R�E���E�j�v�ƌĂ�ł��܂��B
- �Œ�C����8�x�ȉ����炢�ɂȂ�ƐF�Â��͂��߁A5�x�ȉ����炢�̓��������Ɓu�g�t�i�R�E���E�j�v�͋}�ɐi�ނƌ����Ă��܂��B
 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@
-
���̂Ƃ��Ẵ��~�W�E�E�E�g�t�i���~�W�j�ƕ��i�J�G�f�j
- �g�t�i���~�W�j�����i�J�G�f�j���A�ǂ�������N���W�ȃJ�G�f���̍L�t���i���t���j�̑��̂ŁA�A���̕��ޏ�͓����ł��B
- �u�J�G�f�v�Ƃ͂��̗t�̌`���u�J�G���̎�v�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���u�J�w���f�v�ƌĂ�A��������u�J�G�f�v�̌ď̂���ʉ������ƌ����Ă��܂��B
- ���~�W�ƃJ�G�f�́A�t�̌����ڂŎg�������Ă��܂��B�t�̐ꍞ�݂��[���J�G�f���u���������~�W�v�A�t�̐ꍞ�݂��J�G�f���u�������J�G�f�v�ƌĂ�ł��܂��B
- �������A�g�t�i�����悤�j������̑�\�ł���u�C���n���~�W�v�̂��Ƃ��u�C���n�J�G�f�v�Ƃ������Ȃǖ��m�ȋ�ʂ͂Ȃ��悤�ł��B
- �C���n���~�W�̗t�͏����5�`9�ɐꍞ��ł��܂����A������u����͂ɂقւƁv�Ɛ������̂����O�̗R���������ł��B
10��
�R�L�A�i�z�E�L�O�T�E�z�E�L�M�j
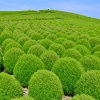 �@�@
�@�@
�R�L�A�Ƃ����A���c�Ђ����C�l��������ϗL���ł��B10����{�ɂ́A�Ă̗ΐF���班�����g�t���n�߁A���{�ɂ͐^���ԂɂȂ邻���ł��B���c�Ђ����C�l������WEB�T�C�g������ƁA�w�������Ŏg�p���Ă���R�L�A�́A��c��Ђ��������p�ɊJ�������i��ł��̂ŁA��ʏ���������ɂ͗��ʂ��Ă��炸�A���w�������������͂ł��܂���B�܂��A�������ł����i��̔̔��͍s���Ă���܂���B�x�Ƃ���A�������̂���ɓ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤�ł��B
-
�H�ׂ�
- �Ƃ�Ԃ�…��N���ł���z�E�L�M�i�z�E�L�O�T�j�̐��n�ʎ��������Ƃ��A��������M���H�������̂ł��B�H�c����َs�ȊO�ł͐��Y����Ă��Ȃ��悤�ł��B�H�c�̓��Y�i�Ƃ��čL���m����悤�ɂȂ�܂����B
- �H��…�v�`�v�`�Ƃ����H�����y���ސH�ނƂ��Ďg���邱�Ƃ������A���̗��Ɋ������鎕�G��Łu���̃L���r�A�v�ȂǂƂ��Ă�Ă��܂��B

- �g��
- �ق���…�͂ꂽ�s�}���ق����Ƃ��Ďg���Ă������߁A�R�L�A�̘a���̓z�E�L�O�T�E�z�E�L�M�ȂǂƌĂ�Ă��܂��B
- �ق���…�R�L�A�����ɍs���Ɓu�̂̂ق����́A����ō���Ă�����v�Ƃ����E���`�N�b���悭���ɂ��܂��B
�@�@�@�@�ł��A�q�ǂ��̂Ƃ��Ɏg���Ă������~�ق����͂��炩�������悤�ȁE�E�E
�@�@�@�@���̂ق����́A���ʂ̎�w��1����30���ō��グ���R�L�A�ڂ����������ł��B
�@�@�@�ihttps://blog.goo.ne.jp/voyage44/e/0fcc56924e36e27c817e5f13aee53749�j - �a�…���~�ق����̍ޗ��ׂĂ݂�ƁA�z�E�L�����R�V�Ƃ����C�l�Ȃ̐A���ł����B
�@�@�@�R�L�A���z�E�L�����R�V�̕������炩���e�͂�����A�t���[�����O�����������A�u�O�~�E�J�[�y�b�g�v
�@�@�@�Ƃ������A��R�̋����u�~���W�v�ł��A�\�����͂����邻���ł��B
 �@
�@ �@
�@
9��
�X�X�L�E�I�M�E���V
 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@
-
�X�X�L
- �H�̎����i�u���Y�ԁi���݂Ȃ����j�v�u���ԁi�������j�v�u�j�[�i�����傤�j�v�u���q�i�Ȃł����j�v�u���сi�ӂ����܁j�v�u���i�����j�v�u���i�͂��j�v�j�̂ЂƂł��B
- �u���i�J���j�v�Ƃ��Ă��X�X�L�́A�����i�J���u�L�j�̑�\�I�ȍޗ��ŁA���������y��ɐ�����X�X�L�́A�W���̋߂��ɑ��������A����I�Ɋ���������������i�J���o�j�ƌĂꊈ�p����Ă��܂����B
- �X�X�L�͈�̂悤�ɁA�����̌s�������ŏW�܂�����ԁi���j�ɂȂ�܂��i�������j�B
- �Ă���H�ɂ����āA�s�̐�[�ɒ���20����30cm���x�̏\���{�ɕ����ꂽ�ԕ�����܂��B�ԕ�͐Ԃ��ۂ��F�����Ă��܂����A��q�i�������͉n�ʁE�������j�ɂ͔����т������āA��S�̂������ۂ��Ȃ�܂��B
- �т͒Z���B��ɂƂ������j��̂��́i䊁F�m�M�j������܂��B
 �@�@
�@�@
- �I�M
- �����ŏ��������i�I�M�j�i���F�n�M�Ƃ͂������܂��j
- �������Ă���ꏊ���D�ރX�X�L�ƈႢ�A�I�M�͉͐�~�̂悤�Ȓn�����ʂ������ꏊ���D�ނ����ł��B�܂��A����������X�X�L�ƈႢ�A�I�M�͂����܂炸�Ɍs���Ԃ��J���Đ����Ă��܂��B
- ��ɂ��Ă���т̐F���Ⴂ�A����Ă݂Ă����炩�ɈႢ�A�����̓I�M�A������ł�����X�X�L�ł��B�܂��A�т͒����A䊁i�m�M�j�͂���܂���B
- ���V
- �����ŏ����ƈ��A���A�b�c
- �w�Î��L�x�ɂ́u�L�����̐�H���ܕS�H�̐��䍑�v�i�Ƃ������͂��̂������Ȃ����������݂̂��ق̂��Ɂj�w���{���I�x�_���ɂ́u�L������ܕS�H����̒n�v�i�Ƃ������͂��̂����������݂̂��ق̂��Ɂj�Ƃ���悤�ɁA���悻��������܂ł́u�A�V�v�ƌĂ�Ă����悤�ł��B
- �e�n�̒r���A�͊݁A���n�ȂǁA���ӂɎ������Ă��܂��B
- ���̌s�ō��������������Łi�悵���j�ƌĂ�̂��痘�p����Ă��܂����B�܂��A�����ނƂ��Ă��œK�Ŋ������Ƃ̕����ւ��Ɍ��݂ł��g���Ă��܂��B
�V���o�i�q�K���o�i�E�q�K���o�i�E�V���E�L�Y�C�Z���E���R���X
 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@
���Ԕފ݉ԁE���ԙ֎ꍹ�i�V���o�i�q�K���o�i�E�V���o�i�}���W���V���Q�j
���Ԃ̗R���͓ˑR�ψقŐ��F�̂̌��ׂ��o���A���r�m���ۂƂ�������ƐԂ��q�K���o�i�ƃV���E�L�Y�C�Z���Ƃ̊|�����킹�ŏo�����ƌ�����������܂��B�܂��A�q�K���o�i�͎O�{�̂̂��ߎ�q���ł��Ȃ����A�q�K���o�i�Ɏ����R�q�K���o�i�͓�{�̂̂��ߎ�q����邱�Ƃ��ł���B���̂��߁A�R�q�K���o�i�ƃV���E�L�Y�C�Z���̊|�����킹�łł����Ƃ����������܂��B
�V���o�i�q�K���o�i�͋�B�암�𒆐S�Ƃ����n��Ŏ�����������悤�ł��B
���ĂŐl�C�̍������R���X�ł��̂ŁA�_�ސ�Ō����锒���q�K���o�i�́A���|��Ƃ��č��o���ꂽ���̂�������܂���B
���ފ�
���ފ݂͔N��2��A�u�t�̂��ފ݁v�u�H�̂��ފ݁v�ƌĂт܂��B�t���̓���H���̓����������i�����イ�ɂ��j�Ƃ��āA�O��3���Ԃ����킹��7���Ԃ����ފ݂ł��B
�ފ݉�
���ފ݂̎����ɂȂ�ƌ��܂��āA��������Ԃ����N�₩�ȐԂ��Ԃ��炫�܂��B�Ԃ��炫�I���A�H�̏I��邱��t���L�тė��N�̏��ĂɌ͂��Ƃ������������Ԃ����A���ł��B�����܂�Ƀ^�l�����邱�Ƃ�����悤�ł����A�ʏ�ފ݉Ԃɂ͎�q���ł��܂���B�n���̗،s�i�����j���������đ����܂��B�ފ݉Ԃ͓Ő�������A���ɗ،s�i�����j�ɑ����܂܂�Ă��܂��B�L�łł��邽�߂ɁA�̐l��_�앨���Q�b�����邽�߂ɁA����̎��ӁE�c��ڂ̂������A���̎��ӂȂǂɐA����ꂽ�悤�ł��B

��B�A�쐼�����A��p�Ɏ������Ă��āA�s��ɉԌa6�`7�p�̑N�₩�ȉ��F���Ԃ��A�������ɐ��֍炩���܂��B���F���ԕق��g�ł��Ă���l�q���A�u���c�q�Q�i���c�̂悤�ɁA�ڂ��ڂ��Ɛ������j�Ђ��j�ɗႦ���v�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B
���@���c�F�����̖��ԓ`���̓����n�̐_�B �傫�Ȋ�ƒ����Ђ��������킦�Ă���B
���R���X
�ފ݉Ԃ͓Ő��������A����b�����Ƃ��ĕ�n�Ȃǂɂ��A����ꂽ���Ƃ���u�������ԁv�u���тƑ��v�u�����Ƃ����낵�v�Ȃǂƕs�g�ȕʖ��������Ă��܂��B���̂悤�Ȗ��O����u���N�������v�Ƃ��āA���{�ł͒��ɐA�͂���̂������Ă����悤�ł��B�������A���̂悤�ȕ������Ȃ������ł͔������ԂƂ��Đl�C������A�i����ǂ��i��Ń��R���X�Ƃ��ăJ���t���ȉԐF�������悤�ɂȂ�܂����B
8��
�j���ƃn�i�j���@�@
-
�j���@�@�y���ށz�ځF�L�W�J�N�V�ځA�ȁF�q�K���o�i�ȁA���F�l�M��
- �j���́A�t�ɏo�Ă����t�������߂����犠�����Ă��A���̌ォ��܂����̐V�����t���L�т܂��B��������ĔN��3��ʂ͎��n���ł��܂��B
- 7�`8�����ɂȂ�ƁA�Ԍs���L�тĂ��܂��i�g�E�����j�B���̃g�E�������ĉԂ��炫�����Ă��Ȃ��ڂ݂̂����ɁA�Ԍs���������犠�����Ď��n�i�H�p�j���܂��B������u�n�i�j���i���j���j�v�ƌĂт܂��B�n�i�j�������n���邽�߂̕i������邻���ł��B
- �Ԃ��炢�Č͂�Ă��A����͒n�㕔���͂ꂽ�����ł��B�t�ɂȂ�Ƃ܂��V�����t���L�тĂ���̂ŁA�ʏ�S�`�T�N�͓����ꏊ�ɐA�����܂܂ō͔|���邱�Ƃ��ł��܂��B
 �@
�@ �@
�@
-
�ʂ��n�i�j���@�@�y���ށz�ځF�L�W�J�N�V�ځA�ȁF�q�K���o�i�ȁA���F�n�i�j����
- ��L�̃j���Ƃ͕ʎ�ŁA�t�ɔ����Ԃ�����u�n�i�j���v�ƌĂԐA��������܂��B�t�ɂ̓j����l�M�̂悤�ȓ���������A�������疽������܂����B
- ���O�͓����ł����A�Ő�������H�p�ɂȂ�܂����B
- ���ɏ�v�Ŏ�Ԃ��炸�ȐA���ł��邽�߁A���[��Ԓd�ɐA�����ςȂ��ɂ��Ă����Ă������܂��B

�n�X�ƃX�C����
- �n�X�́A���{�ł̌Ö����u�n�`�X�v�Ƃ����A�ԑ�̌`���I�̑��Ɍ����Ă��Ƃ���̂��ʐ�
- ���{�ł̓n�X�̎��͂��܂�H����Ȃ��ł����A���������@�̎��́A�؍��⒆���ł悭�H�ׂ��Ă���悤�ł��B��V�̌��\�����҂ł���h�{���̍����H�ނƂ��Ă��l�C�������ł��B�܂��A�s��t���H�ׂ邱�Ƃ��ł��邻���ł��B
- �����R���͘@���Ə����A���{�ł����ʂɐH�ׂ��Ă��܂��B�������A�@���͍��ł͂Ȃ��n���s�ł��B��������{���̍����o�܂��B
 �n�X�i�@�j�@�y���ށz�ځF���}���K�V�ځA�@�ȁF�n�X�ȁA�@���F�n�X��
�n�X�i�@�j�@�y���ށz�ځF���}���K�V�ځA�@�ȁF�n�X�ȁA�@���F�n�X��
-
�X�C�����i���@�j�@�y���ށz�ځF�X�C�����ځA�@�ȁF�X�C�����ȁA�@���F�X�C������
- ���O�̂����́A�u���J�Ԃ��A�ߌ�ɉԂ����̂��A��(�˂�)��ƌ����ĂĐ��@�Ɩ��Â���ꂽ�v�Ƃ����܂��B
- ����̂���A�[���荞�݂�1�{�������~�`�̗t�ƁA���ʂɕ����ԉԂ������ł��B�i�n�X�̗t�ɂ͐ꍞ�݂��Ȃ��A������܂���B�܂��A�Ԃ͐��ʂ�荂���炫�܂��B�j


7��
�q�}����
�q�}�����͊����ď����Ɓu�������v�ł��B���̕����̒ʂ�A�q�}�����̉Ԃ͓����琼�ɑ��z�̓����ɍ��킹�ē����C���[�W������܂��B�������A�����Ă��q�}�������̉Ԃ́A�قƂ�ǂ����������Ă��܂��B

���z�ɔw��������q�}�����̎ʐ^
- ���́A�ڂ݂��ł��n�߂�����̃q�}�����́A���z�̓����ɏ]���đ̂��X���܂��B�s�̐�̕������A���z��ǂ������āA���͓��A�[���͐��ƁA�ƂĂ��悭�����܂��B
- ���������܂��̂́u�I�[�L�V���v�ƌĂ��A���z�������̓������Ƃ����Ă��܂��B���z���̂ڂ��Ă���Ԃ́A�I�[�L�V�������������������Ɣ��Α��̌s�����𐬒������邽�߁A�s�͑��z�̕����ɓ|��܂��B �������邱�Ƃɂ���āA�s��t�ɓ�����������Ղ��Ȃ�A�������������ɂȂ�܂��B�������ނƁA���x�͊O�E�̎h���Ƃ͊W�Ȃ��A���ԂƂ͔��Α��̌s�𐬒������邱�Ƃɂ��A�s�͖�̊Ԃɂ܂����̕����ɖ߂�܂��B
- �Ԃ��炢���Ђ܂��́A���������قǕK�v�Ƃ����A�I�[�L�V���̓������~�܂�ׁA��т��đ��z�̕��������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂��B
�Ђ܂��͖�̂����ɂ͍炩���A�����̊J�Ԃ��������炾�Ƃ����Ă��܂��B���z�̂��铌���������Ă����ԂŁA�J�Ԃ��Đ����z���������~�܂�A�Ԃ̌������Œ肳���̂������ł��B
�A�J�g���{�@�@

��ʓI�Ɂu�A�J�g���{�v�͐ԐF�̃g���{���w���܂����A�A�J�g���{�̃C���[�W�Ƃ��ẮA�H�ɌQ��𐬂��Ĕ��ł���C���[�W������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̃A�J�g���{�́A�u�A�L�A�J�l�i�A�J�l���j�v�ł��B�u�A�L�A�J�l�v�͏����Ɏキ�A�C����30�x����Ɛ���������Ȃ邻���ł��B�H����5������6�����ɍς܂����A�L�A�J�l�́A�����ɂȂ���W���̍����n��i�ꍇ�ɂ���ĕW��2000���[�g�����鈟���R�сj��7������8�����߂����܂��B
�����āA�C�����������Ă����H����ɕ��n�Ɉړ����A���F�������̂��Ԗ������������u�ԃg���{�v�ɂȂ�A�����J�����L��ȂǂŌQ����Ȃ��܂��B�������Ď��B�́A������ˑR���ꂽ�A�L�A�J�l�̑�Q�ɏo����ƂɂȂ�̂ł��B
���̎����ɕ��n�Ō�����A�J�g���{
- �V���E�W���E�g���{�i��WEB�̃g�b�v�̎ʐ^�j�@�V���E�W���E�g���{��
�^���ԂȐF����ۓI�ȃg���{�ł��B���͂����܂ŐԂ��Ȃ�܂��A���̐Ԃ��A�ÓT�����ɋL���ꂽ�ˋ�̓���“���́i���傤���傤�j” �̐Ԃ��v�킹��Ƃ������Ƃ��疼�t����ꂽ�Ƃ����܂��B���́u�V���E�W���E�g���{�v�́A���Ă���Ăɂ����ĕ��n�̃r�I�g�[�v��r�ȂǂŌ����܂��B�i�ʐ^�͏��c���t�����[�K�[�f���ŎB�e�j
�r�܂ŐԂ��A���̕t�����ɑN�₩�Ȟ�F�i�ԁj�̖͗l���������̂������ł��B - �i�c�A�J�l�@�i�ł��A���̎����͂܂��̐F�͐Ԃ��Ȃ��ł��j�@ �A�J�l��
�A�L�A�J�l�����菬�����A�J�g���{�ł��B���n�O�̃i�c�A�J�l�́A���悩�痣��A�߂��̗т̉��ȂǂɈړ����߂��������ŁA�قƂ�ǐl�ڂɂ��Ȃ��悤�ł��B�H�ɂȂ�A���n���̐F���Ԃ��Ȃ邱�됅��ɖ߂�ɐB�������n�܂�܂��B�A�L�A�J�l�Ɠ��l�ɐ��n�����Y�́A�r�ȊO�S�g��������܂ߐԂ��Ȃ�܂��B
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@
�@�@ �@�@ �@
�@6��
�K�N�A�W�T�C�i5��31���X�V�j
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@
�@�@
- ���z�Ԃ̌���͓��{�Ŏ�������K�N�A�W�T�C�ł��B�K�N�A�W�T�C�Ƃ������́A�����ȉԂ̎���ɑ傫�����B�����K�N�i�Ӂj���������Ԃ����͂݁A���ӕ�������悤�ɕ��p���z�i�K�N�j�̂悤���Ƃ����Ƃ��납�疼�t�����ĂƂ����܂��B
- �K�N�A�W�T�C���牀�|��Ƃ��ĉ��ǂ���A�ԏ������`�ł��ׂđ����ԂƂȂ����A�W�T�C���A�K�N�A�W�T�C�Ƌ�ʂ��ăz���A�W�T�C�Ƃ��Ă��܂��B
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@
�@�@
- �K�N�A�W�T�C�̒��S�����ɂ��闱�X���ԂŁA�����Ԃ���������܂��B�܂����ӂ̊z���傫�����B���������Ԃ̒��S�ɂ���Ԃ́A�����ԂŎ�͂ł��Ȃ������ł��B
- �z���A�W�T�C�͑S�Ă������Ԃɗ����Ă���̂ŁA�啔���������Ԃł����͂܂����Ȃ��̂ŁA�}���ő��₷�̂���ʓI�ł��B
5��
�V���E�u�i�n�i�V���E�u�j�i5��17���X�V�j
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@
�@�@
- �H�H�H�Ҋ��ƏҊ��͈Ⴄ�H�H�H
���͏Ҋ��i�V���E�u�j�ɂ́u�T�g�C���Ȃ̏Ҋ��v�Ɓu�A�����Ȃ̏Ҋ��v������܂��B
�E�T�g�C���Ȃ̏Ҋ�(���̎ʐ^�j…�[�߂̐ߋ�ɂ����C�ɕ����ׂ�V���E�u
�@�@�@�@���ׂČ���ƁA�[�߂̐ߋ��Ҋ����̕��K�́A�ޗǎ���ɒ�������`�������悤�ł��B
�@�@�@�@�[�߂̐ߋ�ɏҊ����g�p���镗�K�����{�ɓ`���A�u�����v�u�����v�Ȃǂ̌��t�ɂ�����ꂽ�Ҋ��ɁA
�@�@�@�@�j�̎q��痂����������邱�Ƃ�������悤�ł��B
�E�A�����Ȃ̏Ҋ��i�E�̎ʐ^�j…�쐶�̃m�n�i�V���E�u�����ƂɁA�]�ˎ���𒆐S�ɐ������̕i�킪���ݏo����܂����B
�@�@�@�@����ł�2000��ނ̕i�킪���邻���ł��B - �H�H�H�݂�ȏҊ��H�H�H
 �@�@�@�@
�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@�@
�@�@�@
�E��ԍ��c�A�����ȁB�����ŏ����Ɓu�m��v�Ə����܂��B�×������{�ɂ���A���Łu�J�L�c�o�^�v�Ƃ����܂��B �@�@�@
�E�^�c�A�����ȁB�Ҋ��u�{���̏Ҋ��̓T�g�C���ȁv������́u�m�n�i�V���E�u�v�̉��|��Łu�n�i�V���E�u�v�ł��B
�E��ԉE�c�A�����ȁB�Ҋ��Ə����܂����u�V���E�u�v�Ɠǂ݂܂���B�ʂ̊������g���Ɓu���ځE���ځv�ł��B
�@�@�@�@�@�@�Ԃт�ɖԖڂ̖͗l�����������Ƃ���A���ځE���ځu�A�����v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B
��Wikipedia�ɂ��ƁA�u�n�i�V���E�u�v�̕ʖ��́u�n�i�A�����v�ł���A�k�߂��u�A�����v�ƌĂԕ���������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�u�n�i�V���E�u�v��u�J�L�c�o�^�v���܂߂āA�u�A�����v�ƌď�����K��������B�Ƃ���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ��悭������Ȃ���Ԃł��ˁB
- ��������
- �J�L�c�o�^(���j�@�c���n�ɌQ���E�Ԃт�̍����������͗l
- �n�i�V���E�u�i���j�c�����n�⎼�n�ɌQ���E�Ԃт�̍����ɍג������F�̖͗l
- �A�����i�E�j�@�@�@�c���������ꏊ�ɌQ���E�Ԃт�̍������Ԗږ͗l
�����T�L�c���N�T�@�i5��8���X�V�j
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@
�@�@
- �����T�L�c���N�T�i�A�J�c���N�T�j�ƃV���c���N�T
�������������̐N�������f�[�^�x�[�X�ɂ��ƁA�V���c���N�T�́w�I�����_����̌���̊함�̊Ԃɋl�ߕ��Ƃ��Ďg�p����Ă����̂��C�ŏ��̎����B�q���C�Δ�C�Ή��p�Ƃ��ėA�����ꂽ���̂��蒅�E���z�g�債���ƍl�����Ă���B�x�ƋL�ڂ���Ă��܂��B�����T�L�c���N�T�͓��{�ɂ̓V���c���N�T�Ƌ��ɖq���Ƃ��Ė����ȍ~�ړ����ꂽ�悤�ł��B
�����Łw�l���x�B�ʖ��w�N���[�o�[�x�w�I�����_�Q���Q�x - �K�^�̎l�t�̃N���[�o�[
�N���[�o�[�̏��t�͕��ʂ͎O���B�l�t�ȏ�̃N���[�o�[�͕ψّ̂ł��B�l�t�ɂȂ锭���m����10������1�������ł��B������Ȃ̂���������u���b�L�[�v�Ȃ�ł��傤�ˁB
����Ȏl�t�̃N���[�o�[�̊G��`���܂����H
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@
�@�@
���́A��̊G�͎��͂�����Ƃ��������̂ł��B
���̎ʐ^�̍����V���c���N�T�̗t�E�E�������T�L�c���N�T�̗t�ł��B�n�[�g�ł͂���܂���B
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@

�J�^�o�~�ł�
�}���ȃV���W�N�\�E���̑��N���ł����A�J�^�o�~�̓J�^�o�~�ȃJ�^�o�~���̑��N���ŁA���[��n�E�_�n�Ȃǂł����������Ă��܂��B�S���قȂ�A���ł��B
���Ȃ݂ɁA�J�^�o�~�̕����l�t�ɂȂ�m�����Ⴂ�����ł��B
4��
�l���t�B���@�i4��17���X�V�j
���c�Ђ����C�l����(��錧)�ō͔|����A�����炵���Ԃ���ʂɍL�����Ă���|�X�^�[��f���ň���L���ɂȂ����Ԃ��l���t�B���ł��B
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@
�@�@
- �l���t�B���E�����W�F�V�[�c��ԃ|�s�����[�ȃl���t�B���ł��B ����ɂ��̒��ʼnԐF�ɂ���ĕi�킪�������Ă���A���̒��̂ЂƂɂЂ����C�l�����ɂ��A�����Ă���u�C���V�O�j�X�u���[�v������܂��B
- �l���t�B���E�}�L�����[�^�c�Ԃт�ɓ_��������̃l���t�B���ł��Bmaculata�i�}�L�����[�^�E�}�N���[�^�j �́u���_�̂���v�Ƃ����Ӗ��������ł��B���_�̐��ʂ�ʖ����t�@�C�u�X�|�b�g�Ƃ����܂��B
- �l���t�B�������邱�Ƃ��ł��錧���̏ꏊ…�u�_�ސ�@�l���t�B���v�Ō�����������
�E����͂܉Ԃ̍��i���͌��s�j�c�|�s�[�E�l���t�B���܂��@4��8���i�y�j���j�`5��28���i���j���j
�E�������͌������i���͌��s�j�c�ԃu���O
�E����J�Ԓd��D�t�����[�Z���^�[�i���q�s�j
�E�R�L�A�̗��i���c���j�c�J�ԏ�
�E����C�̎���� �\���C���̋u
�`���[���b�v�@�i4��4���X�V�j
�@�Z�@�N��ɂ���ďK�����w�N�͈Ⴂ�܂����A����͏����w�Z�̗��ȂK���܂��傤�B
 �@
�@
���̊G�̉Ԃ͂Ȃ�ł��傤�H�E�E�E�E�E
�P��������Ă��܂����A�Ԃƌs�Ɨt�������āA�s���܂������ɐL�сA�s�̍�������t���L�сA�Ԃт炪�R����܂��B
�u�`���[���b�v�v�Ɠ���������啔�����Ǝv���܂��B
���ۂ̃`���[���b�v�����Ă݂܂��傤�B
 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@
�@
�ǂ̃`���[���b�v���A�Ԃт炪6���Ɍ����܂��B��͂�B�Ԃт�3���̏�̊G�͊Ԉ���Ă���E�E�E�E�B�Ƃ����Ɏv���Ă͂����܂���B �w�Z�̎��ƂŁA�Ԃ͊O������u�K�N�v�u�Ԃт�v�u�I�V�x�v�u���V�x�v�̏��ɕ���ł���ƏK���܂����B��ʂ̉Ԃł́A�K�N�͉Ԃт�̕t�����̕��ɂ��鏬���ȗ̕����ł����A�`���[���b�v�́A�ڂݑS�̂��A�ΐF����Ԃ̐F�ɕς���Ă����܂��B�܂�A�u�����v���Ԃ�ی삷���ڂ��I����ƁA���x�͐F�Â��ĉԂт�̖�ڂɕς��̂������ł��B�ł��̂ŁA�`���[���b�v�̉Ԃт��3��������ǂ��A�Ԃт�̖�ڂ�������̂�6���Ƃ����������ł��B
3��
�y�M�i�c�N�V�j�i3��22���X�V�j
�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@
�c�N�V�́A3�����y��⓹�[�Ɋ���o���܂��B�c�N�V���͂ꂽ���A�X�M�i�������n���s����L�тĂ��܂��B
�܂�n���s����́A���ނ̌s��n��ɏo���̂ł��B����͖E�q�s�̃c�N�V�ŁA��������̉h�{�s���X�M�i�ł��B���̂悤��2�̖��O�����A���ł����A�w�p�I�ɂ́u�X�M�i�v���W���a���ƂȂ�܂��B
�X�M�i�́u���̖v���C���[�W����`��X�M�i�Ɩ��t����ꂽ�悤�ł��B���̃X�M�i�͖E�q�ő�����V�_�A���ł��̂ŁA�E�q�����肵�A�Y�Ǝ��̑O�t�̂�����܂��B����ɁA�Y�̑O�t�̂ł͐��q���A���̑O�t�̂ł͗�������A���q���j���Ŏ��傫������ƂŃX�M�i�ɂȂ�܂��B�������Ƃ��ẮA�ȊO�ɁA�n���s�������o�������邱�Ƃ��ł��܂��B�n���s�͐ؒf�����Ƃ������甭�肷�鐫�������܂��̂ŁA�X�M�i�������Ă��锨�ɍk�^�@��������ƈ�C�ɃX�M�i���L�����Ă��܂����߁A�쏜����͍̂���ȎG���Ƃ����Ă��܂��B
���Ǝ����̍��@�i3��13���X�V�j
�u�t�߂��v���́A2000�N�ɕi��o�^���ꂽ
�_�ސ쌧�쑫���s�ŗL�̍��ł��B�o�^���ꂽ�����́A�u�������v�̖��œo�^����܂����B �u����g��v�����w���̍��Ƃ��ẴC���[�W�������ł����A�u�t�߂��v���͑��Ǝ��̎����ɍ炭���Ƃ��Đl�C���o�đS���ɍL�܂��Ă��邻���ł��B
���N�́A�ǂ̍����J�Ԃ������A2���ŏЉ�������������̉͒Í��́u���c������܂�v��2��11���`3��12���܂ŊJ����Ă��܂������A������3��6���ɂ͎U��n�߁A�ŏI�̓y��11���E12���͊��S�ȗt���ł����B
����̏t�߂������A3��6���`21���Ɂu�t�،a�E�K�������܂�v���J����Ă��܂����A3��10���ɂ͂قږ��J��Ԃł����B���̎��̎ʐ^������g�p���܂����B
�T�N���̖��B�i�~�c�Z���j

�����o���튯���u���B�v�Ƃ����܂��B���̖��B�́A�Ԃ̒��i�ԓ����B�j�����łȂ��t�ɂ�����܂��i�ԊO���B�j�B�E�̎ʐ^�̊ۂ̒���2�̏o�����肪����ł��B
���̗t�ɂ́A�T�N���P���V�i�����N���V���`�z�R�j��A�����J�V���q�g������ʔ������邱�Ƃ�����܂��B�����̖ђ��i�K�̗c���j�́A���̗t�������Ƃ����ԂɐH�ׂĂ����܂��B
�ԊO���B���番�傳��閨�����߂ăA�����W�܂��Ă��܂��B�A����U�����邱�ƂŁA�����₻�̗c���̐H�Q�����ȗt������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����Ă��܂��B
2��
�T�N���@�i2��22���X�V�j
����̎ʐ^�̃J���d�T�N���́A�Ȃ��Ȃ��U��Ȃ��C���[�W������܂��B�T�N���̉Ԃ̎����ׂĂ݂܂����B
- ����g��……�J�ԁ`���J�܂ł��悻1�T�Ԓ��x�@�@���J����U��܂�4���`1�T�Ԓ��x
- ���d��………�\���C���V�m����1�T�Ԓ��x��ɊJ�ԁ@�@�\���C���V�m���U��܂ł̊��Ԃ�����
- �͒Í�………2����{�ɊJ�Ԃ����{�ɖ��J�@�@�@�J�Ԃ���U��܂�1�J�����x�ƁA�炢�Ă�����Ԃ�����
�Ԃ��U��̂́@�@�i2��22���X�V�j

-
�Ԃт�̍����ɗ��w�Ƃ����זE�w���`������A����܂ŕt�����Ă����ԑ�i�������j����Ԃт炪�藣����邩��ł��B�������ʐ^�̍����悤�ɉԂ��ƎU���Ă��邱�Ƃ�����܂����A�Ԃ��Ɵz��Ɛl�͒N�ł��傤���B�e�^�҂͉��̎ʐ^�ł��B
���̖��O�́A������q���h���E�X�Y���E���W���ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q���g�F�����ق����̂�����ǂ��E�E�E�E�E
 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@

���̉Ԃ̖��́A���̗̊ۂ̓����ɂ���܂��B���ɂ悭�W�܂�q���h����W���́A���������ׂ����̉Ԃ̒��S�ɍ������ނ��Ƃ��ł��܂����A�X�Y���͂��������������ߖ��܂œ͂��܂���A�Ԃ��������Ė����Ȃ߂Ă���̂ł��B
�A���͖����o�����ƂŒ��Ⓓ�Ȃǂ��W�߁A����`���Ă��炢�܂��B�������A�X�Y���̖����r�ߕ��ł͎̏����ɂȂ�܂���B���������Ȃ߂邾���Ȃ̂Łu�����v�Ƃ��Ă��܂��B
�E���E�����E�T�N���̉Ԃ̈Ⴂ�@
 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@
�@�@�u�E���v�E�u�����v�E�u�T�N���v�t�ɍ炭�����͂��ׂăo���ȂʼnԂт�̐���5���̉Ԃ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�c�Ԃ����ċ�ʂ����܂����H
| �J�Ԏ��� | �Ԃт�̌` | �ԕ��i�ԍ[�j �ԂƎ}�̊Ԃ̗̌s |
�Ԃ̍炫�� | |
|---|---|---|---|---|
| �E�� | 2����{���� | �悪�ۂ� | ���� | �߂ɉԂ�1�� �}�ɂւ���悤�ɍ炭 |
| ���� | 3�����{���� | �悪�Ƃ����Ă��� | �ΐF�̉ԕ����Z�� | �߂̕t��������2�ւ̉Ԃ� ��≺�Ȃǂ��܂��܂� �����������č炭 |
| �T�N�� | 3�����{���� | ��ɐꍞ�݂����� | �ΐF�̉ԕ������� | 1�̐߂��炽������̉Ԃ��A���������悤�ɍ炭 |
 �@�A���Y�̉Ԃ͋�ʂł��܂����H
�@�A���Y�̉Ԃ͋�ʂł��܂����H1��
2�̃z�g�P�m�U
 �@�@
�@�@
- TOP�ʐ^���z�g�P�m�U�i���̎ʐ^�j�́A�u���̍��v�Ɗ����ŏ������悤�ɁA�t�̌`�����l�̑��(�@��)�̂悤�Ɍ�����Ƃ����̂����O�̗R�����Ƃ����Ă��܂��B
�z�g�P�m�U�̉Ԃ������ƈ����ς�ƊȒP�ɉԂ��͂���܂��B�Ԃ̍����͓���ɂȂ��Ă��āA���̕������Ȃ߂���z�����肷��ƊÂ����̖������܂��B���͂Ȃ߂��܂����A�{�̂͐H�p�ɂȂ�܂���B - �u�t�̎����v�ɂ��z�g�P�m�U���łĂ��܂��i�Z���E�i�Y�i�E�S�M���E�E�n�R�x���E�z�g�P�m�U�E�X�Y�i�E�X�Y�V���j�B�������A�t�̎����̃z�g�P�m�U�̓R�I�j�^�r���R�i�E�̎ʐ^�j�̂��Ƃł��B���̃z�g�P�m�U�̖��O�̗R�����A�R�I�j�^�r���R�̗t���^���|�|�̗t�̂悤�ɕ��ˏ�ɍL����l�q���A���l�̘@���̂悤���Ƃ����Ƃ��납��t�������O�������ł��B
�t��̏_�炩���V����t���H�p�ɂȂ�܂��B - �T���r�A�A
�c�c�W�A�����T�L�c���N�T�A�X�C�J�Y���A�T�c�L�A�I�V���C�o�i�A�����Q�\�E�A���u�c�o�L�A�T�N�� �Ȃǂ̐A�����A�̂̎q�ǂ��B�ɂ悭�z���Ă����A���ł��B�������A�����J���Ȃ́u���R�ł̃��X�N�v���t�@�C���v�ɂ��ƁA�w�c�c�W�Ȃ̐A���ɂ͓ł������̂������A���ɂ��Ő����������邱�Ƃ�����A���ӂ��K�v�x�Ƃ���܂��B�܂��A�w�n�N�T���V���N�i�Q�x�w�Z�C���E�V���N�i�Q�Ȃǂ̉��|��x�w�����Q�c�c�W�x���̐A��������̓I�ɋ����A���ӂ��Ăт����Ă��܂��B
�u���R�ł̃��X�N�v���t�@�C���v�F
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.html - ���ׂĂ݂��Ƃ���A�����ɂ��Ƃ��Ɛ����Ă��������Q�c�c�W�ł����A���|�p�̕i�������g�߂ŐA�͂���Ă���\��������܂��B���ǂ��̎��̖h�~�̂��߂ɁA�c�c�W�̉Ԃ̖��͔閧�ɂ��Ă����������悢��������܂���B�܂��A�����������Ȃ��̂Ȃ�A�T�c�L�̉Ԃ̖����閧�ɁE�E�E�E�B
